菊池ごはん
2013年2月4日開設。 旅行記がわり、菊池や菊池一族についての備忘録。
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
武朝vs良成親王(五條氏)!?―特別展「八女の名宝」
九州歴史資料館で開催の、特別展「八女の名宝」へ行きました。
目的は後醍醐天皇が懐良親王に持たせたという「金烏の御旗」。普段は年に一度公開されるのみです(もともとは、日干しのために年に一度外に出していたのが慣習化したとのこと)。
その他、後醍醐天皇の綸旨や、懐良親王、良成親王、戦国期の大友家の面々の書状等が展示されていましたが、もちろん写真撮影できるわけもなく、図録を購入して帰りました。
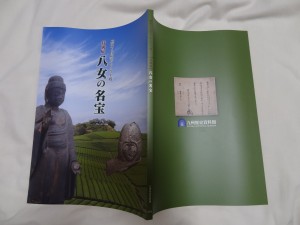
良い展示でしたが(もっと感動するかと思っていましたが…)、五條家文書の中で、二点興味深い事がありました。
一つは、良成親王が「うとうとしい」を連発していること。
前後の文脈から察するに、現代語に訳すと、「だりぃ」「つかれた」「もうどうでもいい」なんでしょうか。結構お疲れのようです。
二つめは、良成親王のいる大杣に攻め寄せてきた「道徹」を、五條頼治が撃退した効を良成親王が賞した元中12(1395)年の感状があったのですが、この「道徹」が「大友氏か、裏切った武朝のこと」と展示では説明されていたのです。
良い展示でしたが(もっと感動するかと思っていましたが…)、五條家文書の中で、二点興味深い事がありました。
一つは、良成親王が「うとうとしい」を連発していること。
前後の文脈から察するに、現代語に訳すと、「だりぃ」「つかれた」「もうどうでもいい」なんでしょうか。結構お疲れのようです。
二つめは、良成親王のいる大杣に攻め寄せてきた「道徹」を、五條頼治が撃退した効を良成親王が賞した元中12(1395)年の感状があったのですが、この「道徹」が「大友氏か、裏切った武朝のこと」と展示では説明されていたのです。
図録の方には、はっきり「菊池武朝撃退の戦功」「北朝へ寝返った道徹(武朝)」とありました。今までいろんな二次三次史料を読んできましたが、武朝が親王の御在所を攻めたというのは初耳でした。
今川了俊が「手強かった菊池は使える」と武朝の菊池復帰を後押ししたという説はあり、復帰に幕府の意向があったのはおそらくその通りなのでしょうが、かといって武朝が親王をあっさり攻めたというのは驚きです。
武朝の子・兼朝がひたすら反幕府だったように、武朝は幕府に認められて復帰しながらも、復帰した後はすぐに手のひらを返したか、少なくとも面従腹背していたと思っていました。なお、兼朝の法名が「透関道徹」ではありますが、このときまだ12歳です(武朝「俺なんか12で家督継いで、了俊と戦ったんだぞ。お前も親王と戦ってこい」とでも言って送り出したんでしょうか)。
武朝や菊池一族のイメージに大きく関係しそうなだけに、気になるところです。
杜の渡しは、大保原の戦い(大原合戦、筑後川の戦い)を前に、菊池方が渡河した地点とも言われます。
背後の土手に上がっても…

ここからではよくわかりませんので、東の橋からみると、言われてみれば何となく渡河しやすそうかなぁ、と思います。
背後の土手に上がっても…
ここからではよくわかりませんので、東の橋からみると、言われてみれば何となく渡河しやすそうかなぁ、と思います。
PR
カレンダー
カテゴリー
最新記事
(12/23)
(05/03)
(04/22)
(03/24)
(02/26)
ブログ内検索
フリーエリア
最新CM
[09/07 名無しのリーク]
[08/01 名無しのリーク]
[07/31 情報漏洩]
[05/23 NONAME]
[04/21 杜小路]

COMMENT